

powered by 地図Z |
城名 | 韮山城(別名:龍城) | ||
| 住所 | 〒410-2143 静岡県伊豆の国市韮山韮山 |
|||
| 入場時間 | − | |||
| 入場料 | − | |||
| 指定文化財 | 市指定文化財 | |||
| 城郭構造 | 梯郭式平山城 | |||
| 天守構造 | なし | |||
| 築城主 | 外山豊前守(堀越公方足利政知の家臣) | |||
| 築城年 | 文明年間(1469年〜1486年) | |||
| 主な改修者 | 伊勢盛時(北条早雲) ※盛時存命中に「北条早雲」の名を使用したことはありません。 |
|||
| 主な城主 | 伊勢氏(後の北条氏)、北条氏規、内藤信成 | |||
| 位置 | 北緯35度3分14秒 東経138度57分20秒 |
|||
| 地図 | 1 | 本丸跡 | ||
| 2 | 二ノ丸跡 | |||
| 3 | 権現平 | |||
| 4 | 三ノ丸跡 | |||
| 5 | 御座所跡 | |||
| 【概要】 韮山城が建つ山は通称「龍城山」といい平山城という形式の城として知られている。韮山城の最初の築城については、明らかではないが、「北条五代記」によると、文明年間(1469〜1486)堀越公方・足利政知の家臣外山豊前守が城をつくったのが始まりとされている。その後、延徳3年(1491)駿河興国寺城にいた伊勢真九郎長氏(盛時、後の北条早雲)が堀越御所の内部の争いにつけ込み、政知の子、茶々丸を滅ぼして伊豆の領主となり、韮山城を本格的に築城したといわれている。早雲は、この地を本拠として小田原城を奪い、後北条氏五代の基を築いた。本拠を小田原に移した北条早雲は、後に韮山に戻り永正16年(1519)88歳で没するまで、33年間ここに住んだ。 現在の韮山高校の校舎の付近を今も御座敷といい。早雲の居館跡であろう。小田原北条氏の西方の守りとして、韮山城は重きをなした。天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐のときは、城主北条氏規(四代氏政の弟)は、約4万の大軍に対して、3千余の将兵をもって、この城を守り通したのである。 北条氏規が城を退いた後、徳川家康は内藤信成を城主としていたが、慶長5年(1600)移封により韮山城は廃城となった。山の高い所に本丸、次いで二ノ丸、権現平、三ノ丸、塩蔵跡や土塁、空堀、内堀などが残っている。 【感想】 城は綺麗に整備されこの時期はとても見やすい状態でした。堀切がいくつも有り北条らしい作りも見られました。 この城跡に北条早雲が暮らしていたかと思うと感慨深いものです。 ただ残念なのは、訪れたときにまったく富士山が見れなかったことでしょうか。 また、この周辺にはいくつもの砦跡があります。城池を挟んだ反対側にも「天ヶ岳砦」があったそうです。 その砦からだとこの韮山城は眼下に見渡せてしまうそうです。豊臣が攻めてきた時もこの砦が利用されたかもしれませんね。 |
登城日 | 2011年1月23日(日) | ||
| LINK | 韮山城-Wikipedia | |||
| 城主家紋 | 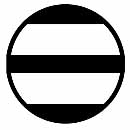 |
【足利二つ引】 (清和源氏義家流) 足利家家紋 |
||
 |
【対い蝶】 (桓武平氏維衝流) 伊勢家家紋 |
|||
 |
【三つ鱗】 (伊勢平氏流) 後北条家家紋 |
|||
| 【韮山城全景】 城西側より見た全景。 |
【堀切跡】 |
城池親水公園】 左に曲がれば韮山城址、直進した右側が公園となっている。 |
 |
||
| 【韮山城全景】 城池越し東側から見た城址全景。この城池は城の堀としても機能していたと思われる。 |
||
| 【堀】 登城口右側に残る堀。 |
【登城道1】 | 【登城道1】 登城道は途中鍵形になっており枡形が形成されていたと思われる。 |
| 【三ノ丸跡】 現在は韮山高校のテニスコートになっている。 |
【三ノ丸の土塁】 | 【堀切】 この先は御座敷跡(韮山高校)へ降りられるようになっているが当時ここに虎口があったかは不明。 |
| 【御座敷跡】 現在は韮山高校になっていますが、校舎部分にに城主の暮らしていた館があったそうです。 |
【虎口】 三ノ丸と権現平を繋ぐ虎口。 |
【権現平】 |
| 【権現平】 現在は小高い場所に熊野神社が建っているが元は櫓があったと考えられる。 |
【熊野神社鳥居】 |
【熊野神社】 ここに櫓があったと思われる。 |
| 【虎口】 この虎口は城下に繋がっている。登城道2となる。ここも途中鍵形になっている。 |
【登城道3】 左側は二ノ丸へ続く道、右側は御座敷跡へ続く道になる。 |
【二ノ丸跡】 登城道の左側に広がる曲輪で周囲は土塁で囲まれている。 |
| 【二ノ丸跡】 |
【二ノ丸虎口】 この先は土橋があり堀切がある。 |
【土橋と堀切】 |
| 【縦堀】 堀切からそのまま縦堀になっているようである。 |
【土橋と堀切】 本丸側より撮影。 |
【本丸登り口】 |
| 【本丸跡】 | 【本丸奥の虎口】 本丸より奥に行くことができる。 |
【弾薬庫跡】 本丸奥には土塁に囲まれた2つの空間がある。この空間は弾薬庫だったと考えられています。 |
| 【弾薬庫跡】 | 【韮山城最南端】 この箇所はちょっとした平場になっているので見張台でもあったと思われる。 |
【弾薬庫の虎口】 |
| 【本丸下の通路】 本丸から土塁上をあるいて最南端まで行けるが、本丸に上がらなくても通路が下にある。 |
【登城道2】 先に説明している権現平から城下に行くための虎口である。 写真のように鍵形になっており、ここも枡形になていたと考えられる。 |
【登城道2】 |
| 【登城道2】 登り口である。 |
【船入跡?】 登城道2の登り口付近にある窪地。 |
【堀切】 |
| 〜蛭ヶ島(源頼朝配流の地跡)〜 この辺りを蛭ヶ島といい、平治の乱で敗れた源義朝の嫡子、兵衛佐頼朝配流の地と言われている。蛭ヶ島とは狩野川の中州の一つだったと想像される。 嬰暦元年(1160)14歳でこの地に流された頼朝は、治承4年(1180)34歳で旗挙げ、やがては鎌倉幕府創設を成し遂げることとなるが、配流二十年間における住居跡などの細部は明らかでない。しかし、「吾妻鏡」治承4年の記事によれば、山本攻め(頼朝旗挙げ)の頃は、妻政子の父、北条時政の館に居住し館内で挙兵準備を整えたとある。このことから考えると、頼朝は、北条政子と結ばれる治承元年(1177)頃までの17年間を、ここ蛭ヶ島で過ごしたとも言えます。 |
||
| 【江川邸】(重要文化財) | 【枡形】 江戸時代代官が外出する際、人数を揃えるのに使われていました。幕末には、農兵の訓練所としても利用されました。 |
【表門】 三間一戸の薬医門。 |
| 【主屋-玄関】 玄関前にはきささげの木が生えており、北条早雲が植えたとの言い伝えがある古木。 |
【通路】 | 【役所跡】 代官所の役人が執務した建物のあった場所。 |
| 【主屋-土間】 50坪の広さがある。 |
【ボートホーウィッスル砲車】 安政元年(1854)にペリーから幕府に贈られたものと推定される。砲身と砲弾は模型。 |
【パン焼き窯と鉄鍋】 天保13年(1842)4月12日、江川英龍の命により、邸内に築かれた窯で、初めてパンが焼かれました。この初めてパンが焼かれた4月12日が、現在「パンの日」になっています。 |
| 【主屋-屋根裏の架構(小屋組み)】 | 【生き柱】 江川氏がこの地に移り住んできたとき、生えていた欅の木をそのまま柱として利用したとされる柱。 |
【主屋-台所】 |
| 【主屋-中庭】 | 【主屋】 手前から控の間、使者の間、玄関、塾の間となっている。 |
【塾の間】 |
| 【西蔵】 幕末頃の建築で、正面から見ると将棋の駒の様な形をしていることから駒蔵とも呼ばれる。また、四方の壁が内側に向かってわずかに傾いた「四方ころび」といわれる技法で建てられている。 |
【南米蔵・北米蔵】 | 【欅と井戸】 元々栴檀の木に宿った宿り木で、親木が枯れた後、欅だけが残って成長し、現在の姿となった。 |
| 【井戸】 江戸期以前に掘られ、名水が出、生活用水と共に江川酒の醸造にも使用されたと言われる井戸です。 |
【主屋】 | 【武器庫】 |
| 【パン祖の碑】 | 【庭に咲いていた梅】 | 【裏門】 |
| 【裏門の矢傷】 | 【裏門】 | 【伊豆の国韮山郷郷土資料館】 |
| 【蔵屋鳴沢・反射炉】 左はお土産屋、右が反射炉(国指定史跡)。 |
【橋】 川に架かる橋の欄干部分が砲弾とは洒落ています。 |
【江川英龍像】 |
| 【反射炉】 ここで品川台場の大砲を製造した。 |
【反射炉の碑】 | 【24ポンドカノン砲】 ここで一番多く製造された砲で、同じものが品川台場に置かれていたと考えられる。 |
| 【鋳口と焚口】 左側が焚口、右側が鋳口。 |
【反射炉】 | 【鋳台跡】 |
 |
 |
ジャンル:レストラン 店名:蔵屋鳴沢 住所:静岡県伊豆の国市中272-1 TEL:055-949-1208 営業時間 月〜木:11:00〜15:00(オーダーストップ14;30) 金:11:00〜22:00(オーダーストップ21:00) 土日祝:10:00〜22:00(オーダーストップ21:00) 定休日:年中無休 このレストランの売りは、地ビールとは網焼きです。 地ビールは飲み比べがいろいろ出来ます。 私が食べたのは地ビールで煮込んだ牛肉を使ったビーフシチューランチセットです。 肉は柔らかく美味しかったですよ。 |